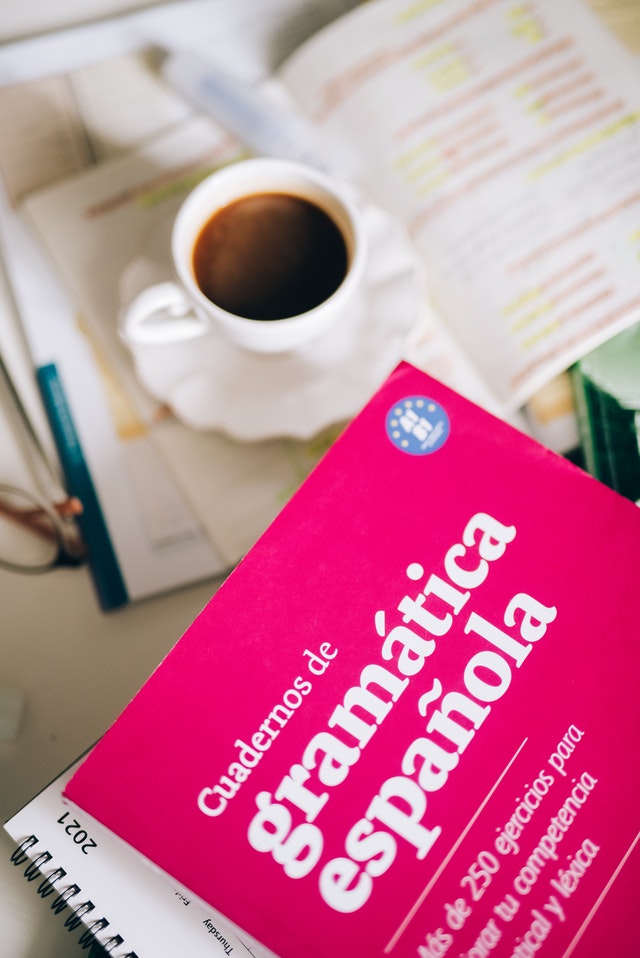スペイン、中学生の100人に9人が留年、OECDトップ
問題はシステム? 教育改革の議論も紛糾
- 2021/9/30
スペインでは、義務教育期間中の留年が認められているが、留年率の高さが長年問題視されている。
9月16日に公表された経済協力開発機構(OECD)の新しい報告書「図表でみる教育2021(Education at a Glance 2021)」でも、スペインの学校での留年率の高さが改めて明らかになり、同国の複数の報道機関が報じた。
ニート率の高さにも関係か
同報告書の内容を報じた「ラ・バングアルディア」(電子版)によると、同国の前期中等教育(スペインでは12~14歳に相当)において、2019年の留年率は8.7%、平均1.9%のOECD諸国の中で最も高い割合となった。EUの平均は2.2%という。また、後期中等教育(同15~18歳に相当)でも7.9%と、チェコ共和国の8.2%に次いで2位となった。
同報告書では、就業や就学もしていない18歳から24歳、いわゆるニートの割合が、スペインでは2020年に22.0%に上り、25.5%のイタリアに次いでOECD諸国中第2位に、というデータも公表された。
「エル・パイス」にコメントしたOECDの研究員は、留年率の高さがニート率の高さにも関係があると指摘。留年は格差を拡大し、生徒の自尊心にも悪影響を及ぼす可能性があるという研究もあり、長期的に見ると、留年した生徒は成績が悪くなり、退学する可能性も増える、なとどしている。
原因は慣習? 統計の問題?
同国の公共放送「RTVE」は、報告書の発表を受けて、留年率の高さの理由を分析。
同メディアによると、OECD生徒の学習到達度調査では、スペインの総合成績は、OECD平均のそれほど下でもないが、同程度の国よりも留年率が高い。昨年7月には、アレハンドロ・ティアナ教育省長官は「他の教育システムでは留年にならないのに、スペインではなっている」と述べたそうだ。
複数の専門家は「留年の慣習」に原因があると指摘。留年は「例外的」な選択肢であるべきとし、生徒の「汚名」につながること、一部科目で落第でも全課程を繰り返させる時間の無駄、などのデメリットを強調した。
教員を指導する立場の教職者ピル・ドピコ氏は「私が学生の頃は、留年は珍しかったが、今は当たり前になっている…留年は悪用されている」などとコメント。
留年率減少に賛成派の専門家は、改善のためにはアプローチの変更が最も重要だと考えているという。マドリード自治大学のエレナ・マルティン・オルテガ教授(発達・教育心理学)は「他の国は、何年も前にOECDのアドバイザーが発表した論文のタイトルの『カリキュラムを繰り返すか、再編成するか』という言葉に反応した…つまり生徒の特性に合わせて支援に修正を加えた」と同メディアに話している。
かつては留年率の高さは「フランス病」と呼ばれていたにも関わらず、その数字を改善したフランスなどを例に挙げ「他の国とスペインの1番の違いは、留年を当たり前と思わないこと。他の国では多様化が進んでおり、生徒は進級したら得意なことに集中するか、そのうち補っていくか」と、マドリード・コンプルテンセ大学のフェルナンデス・エングイタ教授(社会学)は同メディアにコメントした。
一方、マドリード・コンプルテンセ大学のフリオ・カラバニャ教授(社会学)はこれらの専門家とは違った意見で、留年率の高さには主に2つの理由があるとコメント。1つは、スペインでは他の国とは異なり、「資格取得を目的とした」教育が行われており、プログラムに忠実に従うことが求められるため。もう1つの理由は、他の欧州諸国では「成熟度に応じて」就学開始年齢が決められるのに対し、スペインでは一律で6歳とされていること。そのため、留年率の高さは「スペインではそのように教育が編制されているだけ」と、OECDの警告を「誤り」とまで踏み込み、「留年率が低い国の方が成績がいいとは誰も証明できない…授業を行う上でも同質の集団に教える方が簡単で効果的でメリットがある」などと、現行制度を肯定した。
また、「エル・エスパニョール」には1クラスあたり30人から38人という生徒数が原因とする意見も。2020年から2021年にかけては留年者数が減ったとし、「(新型コロナウイルスの)パンデミックによる健康上の問題から、生徒の比率が減らされたため」と分析する教職員の話も紹介されている。
教育改革にも批判続々
同国では、留年者数の減少などを目指す教育改革が近年議論されている。「エル・パイス」によると、この改革では、以前は義務教育機関を通じて3回まで可能だった留年を、今後は2回に。留年決定の目安は2教科落第だったが、今後はこの数字を問わないことにし、最終的には留年を例外的なものにするという。
しかし、報告書について報じた「エル・ムンド」は、この改革について、留年を問題として捉えているのみで、何かがうまくいっていないかを突き止めていないことだと指摘する。
マドリッドのレイ・フアン・カルロス大学のホルヘ・サインス教授(応用経済学)は、「政府の戦略は、追試を廃止し、科目を落第しても進級できるようにし、教育課程のコスト減をすることだ」とし「構図のごまかしだ。あるレベルに合格すると、より多くのことを知っているように見えるが、問題は長期的に定着し、長期的にはさらなる不平等を生むことになる」と、同紙にコメント。
また、「アラ」も社説でこうした枠組みは留年率のデータのロンダリングにつながる、と批判している。