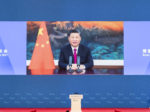モンゴルの障害者を描いた「STAIRS」が東京の映画祭で受賞
ゾルジャルガル監督「もっと強く、アクティビストであれ」
- 2021/8/5
舗装されていない道路にスロープのない階段、昇降リフトのないバス―-。外の世界に踏み出した車椅子利用者の行く手を阻むように、次々と壁が立ちはだかる。モンゴルのゲル地区に暮らす障害者から見た同国社会を描いた短編映画が、アジア最大級の国際短編映画祭「ショートショートフィルムフェスティバル&アジア(SSFF&ASIA、2021年6月30日まで開催)」で、「Make impossible possible(不可能を可能にする)」を伝えるバイオジェン・アワードを受賞した。12分の映像に込めた祖国への思いについて、ゾルジャルガル・プレブダシ監督に聞いた。
日本の大学で学んだ映像技術
主人公は、車椅子生活をしている男性だ。手先の器用さを生かし、妹やその友人の女の子たちの長い髪をお団子にまとめてやったり、編み込んだり、リボンを飾ってあげたりしては、彼女たちの喜ぶ姿を見ることを日々の楽しみにしている。そんな彼が、妹に背中を押されてある決意をする。夢を見つけて決断し、覚悟を決め、立ちはだかる問題を自分で解決していく男性の静かで力強い姿が印象的な作品だ。
映画を制作したゾルジャルガル監督は、「障害者にも夢があることを伝えると同時に、障害者自身が、夢の実現のために行動する姿を描きたかった」と話す。その背景にあるのは、「障害者はもっと強く、アクティビストになるべき」という、強い思いだ。タイトル「STAIRS」には、健常者には何ということのない階段が、車椅子利用者にはこれほどまで大きな壁になり得るのだという意味を込めた。
幼い頃から映画を観ることが好きで、映画の道に進みたかったが、家族に反対されて、一時は物理や数学の道を志した。しかし、高校時代に演劇部で活動したのを機に映画制作の夢が再燃し、奨学金を得て2008年に来日。桜美林大学の映画学科で4年間、映像制作を学んだ。現在はモンゴルを拠点に、子どもの虐待や貧困、女性問題などをテーマにした映画を撮り続けている。
原体験となった介助アルバイト
最初に障害者の問題に接したのも、高校時代だった。日本式教育を取り入れていることで知られる新モンゴル高校に在学中、サマースクールに参加して、モンゴルの障害者団体の活動状況や、障害者を取り巻く環境について調査した。その後、来日して、昇降機のついたバスや、駅に設置されたエレベーター、道路やホームの点字ブロックなどを見て、モンゴルのバリアフリー化がいかに遅れているか痛感したという。
日本滞在中は、ある障害者の自宅に2年間通って介助アルバイトを続けた。自由に動けないにも関わらず、ニンジンの切り方や味付けなど料理を一から教えてくれたほか、部屋の掃除や片付けの指示もいつも的確で、日々、主体的に生活する姿に胸打たれた。
介助のための研修を受講していたある日、1枚の写真に強い衝撃を受けた。写っていたのは、脳性まひの男性が駅前の路上に横たわりながら、自分の権利を求めて通行人にチラシを配っている姿だった。
この写真を機に、日本もかつては障害者の外出や行動が制限されていたが、1970年代に障害者自身による権利運動が盛んになったことで社会制度の変革につながったという歴史を知ったゾルジャルガル監督。「モンゴルの現状を変えるためには、かつての日本と同じように、障害当事者が自分の要求を主張し、自ら行動しなければならない」と確信したことが、今回の構想につながった。
18人の知的障害者と共に制作
「STAIRS」は、障害者とともに制作した作品だ。主役を演じた男性が実際の車椅子生活者であっただけでなく、総勢約60人のスタッフのうち18人は知的障害者だったという。
彼らは、2009年から各国の障害者に映画制作を教えているオーストラリアのNPO、バスストップフィルムズが、モンゴルで文化芸術の振興を目指すNGOのアートカウンセルモンゴルと2019年に実施したワークショップの参加者たちだ。その後、実際に映画を制作する段階で監督として声をかけられたゾルジャルガルさんは、カメラマンやメイクアップのアシスタント、カチンコを打つ係、カメラリハーサルで役者の代わりにポジションに立つ係など、一人一人に役割を与えて制作を開始したが、最初はかなり苦戦した。
障害のあるスタッフの一人に、すぐに癇癪を起こす17歳の男性がいた。撮影初日、兄と妹が砂利道を通るシーンを日暮れまでに撮り終えなければと焦っていたゾルジャルガル監督は、男性が癇癪を起こして撮影が中断したことに苛立ち、思わず怒鳴りつけてしまった。一層興奮する男性を見てすぐに我に返り、自己嫌悪にかられたが、同時にあることに気付き、はっとした。
「障害者と長年にわたり映画を作って来たバスストップフィルムズのスタッフには、彼らとうまく付き合う秘訣があると思い込んでいたのですが、そんなものはどこにもありませんでした。人間は皆、違うのだから、障害の有無に関わらず、ただ一人一人と丁寧に向き合えば良かったのです」
この出来事を機に、撮影スケジュールへのプレッシャーや、必要以上の気負いを捨てて自分のペースでスタッフと接することができるようになったゾルジャルガル監督。すると、新たな疑問が出てきた。スタッフが皆、毎日14時間近く現場で作業に追われているにも関わらず、障害のある18人は6時間前後で帰宅していることへの違和感だった。
そこで監督は、ある決断をする。彼らがすぐに飽きないように役割を定期的に交代させながら、皆と同じ時間、作業に加わってもらうことにしたのだ。不安がる保護者には「あなたのお子さんは大人なのですから、信じてあげてください」と伝え、目を輝かせて作業に取り組む彼らの姿を見てもらうようにした。それだけに、映画が完成した時は、皆、大変な喜びようだった。「うちの子はすぐに“お腹が空いた”“疲れた”と言うので長時間働くのは難しいと思っていましたが、一緒に働けて良かったです」と言う保護者もいたという。