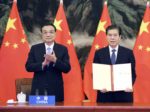進むタイの少子高齢化と地方分権
横展開の期待集まる自治体主導型ケア施設
- 2020/3/9
典型的な街で生まれた先進的な取り組み
ショッピングセンターや映画館が建ち並ぶタイの首都、バンコク。洒落たレストランでも着飾った若者たちで賑わっており、アジアらしい活気と熱気を実感することができる。
そのバンコクから40kmほど北に位置するブンイトー市で2019年12月、ある施設がテスト運営を開始し、注目を集めている。タイ国内で初めて自治体が主体となって設立した本格的な高齢者デイケア&デイサービスセンターだ。現在は、高齢者を日に4~5人ずつ受け入れており、本格的な営業開始は今年4月ごろの予定だ。
利用者たちは、毎朝9時頃に自宅から市の送迎車に乗ってセンターに到着し、市の医師の健康診断を受けたり、市の看護師が行う生活環境に関する聞き取りに応じたりした後、ボランティアと会話を楽しんだり、市の理学療法士のマッサージを受けたりして過ごす。この日の昼食のメニューは、鶏肉の生姜炒めとスープ、パパイヤのデザートだった。
この取り組みが、実はいまタイで非常に注目をされている。住宅地や工場、農地などが点在する人口3万人ほどの典型的な郊外の街、ブンイトー市で、なぜ、他の街に先んじて先進的な取り組みが生まれたのだろうか。その背景を取材した。
公的医療サービスの普及で平均寿命が進展
タイはかつて、他の開発途上国と同じように出生率が高く、大家族が普通であった。しかし、そんなタイ社会が、近年、大きく変わりつつある。
例えば、近年の両国の合計特殊出生率(一人の女性が生涯に産むこどもの数)を見ると、日本が1.43人、タイも1.53人と、ほぼ同じ低い水準にとどまっている。一方、全人口に占める60歳以上の割合は、タイが17.1%と、日本の34.5%に比べれば、まだ低いものの、この国は、日本がかつて世界で最も速く高齢社会になった当時を上回るスピードで高齢化が進展しており、要介護高齢者の数が急速に増大しているのだ。実際、冒頭の通り、バンコクでは若者を多く見かけるが、郊外に行けば、途端に高齢者を見かけることが多くなってくる。
その背景には、いくつかの要因が挙げられる。中でも、少子化と並び、平均寿命が大きく伸びたことも大きい。タイでは2002年、ユニバーサル ヘルス カバレージ(UHC)と呼ばれる公的医療サービス、すなわち低価格で一定レベルの医療サービスを全国民に提供する制度が開始された。これによって、経済的に裕福ではない人でも、皆が等しく標準的な医療サービスを受けることが可能になったことから、平均寿命が伸びたと言われている。
世代間で広がる乖離とゆらぐ在宅介護
ところが、UHCの整備が進み高齢者が増える一方、介護が必要な高齢者に対する公的な支援制度の整備は遅れている。具体的には、十分な介護保険も、国民全体を対象とした年金制度も存在せず、困窮高齢者への経済的支援は少額の高齢者手当支給にとどまっている。公的な入居施設も限られており、今後、十分な数を整備できる財政的な裏付けもない。タイ政府の基本方針の中でも、家族やボランティアによる在宅介護の推進が掲げられている。
タイの人々にヒアリングをしてみると、「タイでは家族のつながりが深いから、家族が高齢者の介護をするのが当然のことだと思う」「地域には助け合いの精神もあるため大丈夫」といったように、在宅介護の実施や継続を楽観視する意見をしばしば耳にする。実際、筆者は2019年4月、農村部を回り、高齢者に「今後、あなたの介護が必要になった場合は、誰が面倒をみてくれるのか?」と尋ねてみたのだが、やはり自分の息子や娘に期待する声が圧倒的に多かった。
しかし、さらに質問を続けると、多くの場合、彼らの息子や娘たちは現時点では遠く離れた都市部で働いていることが分かった。つまり、高齢者の多くは、自分に介護が必要になったら、子どもが現在の仕事を辞めて地元に戻って来てくれることを期待していることの表れだと言えよう。だが、現実的には、長く故郷を離れ、都市部で新しい生活基盤を築いている子ども世帯が生活の拠点を地元に戻すことは容易ではなく、そうしたケースはかなり限られてくると思われる。孫が生まれ、学校に通い始めてからはなおさらだ。「慣れ親しんだ家で、子どもや孫の介護を受けながら余生を送る」といった理想論が、早晩、破綻するのは、明らかだ。