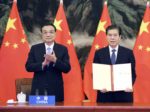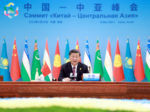進むタイの少子高齢化と地方分権
横展開の期待集まる自治体主導型ケア施設
- 2020/3/9
「国立」にない強みとは
こうした状況を踏まえ、タイでは近年、家族や近隣に住む親族による従来の介護スタイルを基本としながらも、それを支える社会的な仕組みの立ち上げが喫緊の課題となっている。
前出のブンイトー市立高齢者デイケア&デイサービスセンターも、そのような問題意識を背景に設立された。外出が困難な高齢者を日中、受け入れる場をつくることによって、高齢者が自宅に引きこもることなくさまざまな社会活動に参加できると同時に、家族の負担を軽減できるという意味がある。
さらに、この施設が「市立」であることの意味が非常に大きい。
タイには、実はこれまでにも国立病院の付属施設に似たような施設があった。こうした施設は、国立病院に所属する医師や看護師、理学療法士といった専門職と連携した手厚い体制が売りだったものの、サービスの対象は基本的に国立病院の周辺住民に限られ、タイ全土をカバーすることはできていなかった。
その点、このほどブンイトー市によって設立されたこのセンターは、タイ全土にある市が運営するモデルであり、医師や看護師、理学療法士などの専門職を市が雇用し、地域の実情に合わせたセンターを運営することが目指されている。将来的には、民間に運営を委託した方がより効率的だとの考え方もあろうが、それはまだ先の話であり、これまで国立施設しかなかった分野に市立の施設が誕生したこと自体が、まずは画期的だと言えよう。
モデル事業が生まれた3つの理由
今回、全国に先駆け、ブンイトー市でこの取り組みが生まれた背景には3つの要因が挙げられる。
第一に、地方分権化を進めたいタイ政府の基本方針がある。近年、首相を議長とする地方分権化委員会によって地方分権化が進められ、予算と権限が地方自治体に移管されつつあるのだ。
第二に、住民のニーズに応えようとした市側の意欲だ。住民参加型で徹底的に議論した結果、高齢者からは「住み慣れた地域に住み続けたい」「社会に参加し続けたい」といった声が、また、彼らの家族からは「家で面倒をみてあげたいが、自分たちだけでは限界がある」との声が寄せられたという。高齢者と家族、双方の切実な要望をすくい上げようとした行政の姿勢なくして、今回の構想は実現しなかった。
第三に、ブンイトー市のランサン市長の強いリーダーシップだ。市長自らが旗振り役として音頭を取ったからこそ、この構想は長い時間を要することなく具体的な形になった。
同施設は今後、数カ月間の試行期間を経て、2020年5月より本格的に運営を開始する予定だという。人員や予算が潤沢な国立の施設と違い、設立から運営まで一貫して自治体が主体となる施設ができるということは、予算的にも、人員的にも、他の自治体でも十分に設立可能であるということであり、地方分権化のタイ政府方針とあいまって、今後、横展開していくことが期待されている。
ランサン市長は、「この施設の取り組みは、あくまでブンイトー市民のための取り組みだが、将来的には、タイ全土の人々に裨益するモデルとなることを意識している」と語り、「ここでの取り組みが他の市に広がれば、各地で改善が加えられたり、協力関係が結ばれたりして、結果的にはブンイトー市民にとってもさらなる利益につながるはずです」と、期待を寄せる。その言葉通り、ブンイトー市はすでに他の自治体からの見学を受け入れ始めており、ラヨン県タップマー市と公式に協力協定を締結するための準備も進んでいる。
ブンイトー市の取り組みはまだまだ開始されたばかりだが、これからの展開が期待される。