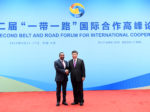【書評】宇田有三著『ロヒンギャ 差別の深層』ロヒンギャ問題をどう考えるべきか
ミャンマーの「土着化したムスリム集団」を論じた好著
- 2020/10/5
「ロヒンギャ問題」を適切に理解するための情報を持ち合わせている日本人は限られている。メディアによる報道は2016年から18年をピークに盛り上がりを見せたが、最近は大幅に減っている。
一方で、ここ1年半ほどの間に日本語でロヒンギャ問題を取り上げた本は本書を含め4点出版され、いずれもそれぞれの専門性を生かした優れた議論を展開している(文末参照)。
世界の中でも日本はロヒンギャ問題に関する優れた著作に恵まれているほうである。英語でロヒンギャ問題をとりあげた本は多いが、その多くは難民としての彼らの悲惨さを人権問題に焦点を合わせて論じ、問題理解を深めるにあたって取り上げるべきロヒンギャをめぐる歴史的背景や、1948年のミャンマー独立後の扱われ方、1962年以降の軍部による強権支配とそれによるミャンマー国民のロヒンギャに対する視線の冷淡化など、多角的に問題の深層に切り込もうとする姿勢は弱い(無論、優れた分析をおこなった本もある)。
本書は、ミャンマーに関わり続けて25年以上のフォトジャーナリストによって書かれた本である。学術書の体裁はとっていないが、ロヒンギャがミャンマーでこれまで置かれてきた状況と、そこに至った歴史的経緯、国連を軸とする国際社会の反応と問題点に加え、「民族」「国民」「先住民」「先住民族」といった近代用語の定義にまで遡って問題の本質に迫り、この問題をどう解決に向かわせるのがよいのかを問う骨太の著作である。著者はロヒンギャを「民族」としてではなく、ミャンマー国内で土着化したムスリム集団の一つである「ロヒンギャ・ムスリム」としてとらえるべきだと結論づける。
その結論に至るまでの基本的な「問い」を、著者は「ロヒンギャ難民問題」「ロヒンギャ問題」「ミャンマー問題」「ミャンマーに対する日本側(我々)の視点の問題」の4つに分けて示し、そもそもこの4つの「問い」を「ごちゃまぜにしている」ために、国際社会におけるロヒンギャ問題の理解が進まないのだと述べる。この指摘には評者も同意する。
第1章「ロヒンギャ難民キャンプへ」では、最初の「問い」である「ロヒンギャ難民問題」がとりあげられている。フォトジャーナリストとしての自己批判から始まり、難民キャンプで撮影した「訴えかけるようなまなざしの」ロヒンギャ少女の写真を示しながら、これを記事や講演会で提示することによって、人々に「かわいそうだ」というレベルの注意を喚起することはできても、何らかの行動を実際に起こさせるまでの動機を作り出すには至らないと語る。
一方で撮影した本人(著者)は、「自分は弱者の立場に寄り添っているという錯覚」を抱きかねないと自省する。そのうえで、写真だけではとても伝え切れないミャンマーとバングラデシュ国境の様子や、バングラデシュのロヒンギャ難民キャンプの実情と問題点を、何度かにわたる現地取材に基づいて論じている。そこでは国連や援助団体の支援を受ける「公式」キャンプと、それ以外の「非公式」キャンプの尋常ではない格差が指摘され、その要因の分析が試みられる。100万人の難民を受け入れたバングラデシュ南部のコックスバザール一帯の事情についても述べられ、「貧しいわが国がロヒンギャを受け入れる余裕はない」という現地の人の感想が紹介される。
こうして難民キャンプとその周辺をめぐる一連の厳しい状況を読者にわかりやすく述べたうえで、著者は二つ目と三つ目の「問い」である「ロヒンギャ問題」と「ミャンマー問題」に筆を進める。
この二つは解くことが特に難しい「方程式」である。それに正面から取り組んだのが本書の骨格を成す第2章であり、ここでは質疑応答形式の文章が110ページ以上(本書の約3分の1)つづく。これは、基本知識を持ち合わせない読者を意識したジャーナリストらしい書き方である。
この章で扱われる論点は実に幅広い。ロヒンギャ報道の変遷と国際社会の理解不足にはじまり、ミャンマーの国家・社会・宗教・民族をめぐるクリティカルな分析、国内在住ムスリムの特徴と彼らのアイデンティティ、多数派仏教徒との関係、ロヒンギャの実態(呼称・言語・暮らし、彼らとほかの国内在住ムスリム集団との関係)、独立後のミャンマー社会とロヒンギャとの関係(特に1982年制定の市民権法の問題点)、ロヒンギャ問題の発生過程(ベンガル地方から現ラカイン州北西部に定住するに至った歴史的経緯)、多数派のラカイン民族の特徴、ロヒンギャをめぐる4つの対立する解釈の整理、アウンサンスーチーの姿勢、政府によってテロリスト認定されたアラカン・ロヒンギャ救世軍(ARSA)の特徴、国境の麻薬取引問題、そして問題解決への道筋を含め、すべてがわかりやすく述べられる。
著者は「ロヒンギャ問題」の根源について、ミャンマーの軍部独裁期(1962-2011)において、軍が自らの権力基盤強化のために国民のイスラームに対する差別的な潜在意識を刺激して作り出した政策が生み出したものであると結論付ける。同時に、一般のロヒンギャ住民は「民族」としてよりも「ムスリム」としてのアイデンティティのほうを強く持ち、それに基づいてミャンマー国内(ラカイン州北西部)で安心して暮らしたいという願いを抱いていることが明らかにされる。