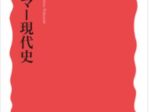ベトナム映画の今昔 変わる作風と映画館事情
プロパガンダ、娯楽コンテンツから世相を映す鏡へ
- 2019/9/10
”ベトナム映画”と聞くと、どんなイメージをお持ちだろうか。トラン・アン・ユン監督の「青いパパイヤの香り」、それとも「ラ・マン(愛人)」「インドシナ」。「Co Ba Saigon(仕立て屋 サイゴンを生きる)」を挙げる人は、かなりの映画通。筆者は学生時代に広くアジア映画に魅せられたひとり。ベトナムとの出会いは、映画との出会いでもあった。2000年前後には映画のコラムを日本に向けて発信していたこともあるが、ここ数年すっかりご無沙汰だった。昨年あたりから久しぶりに再開した”私的ベトナム映画活動”。作品の多様化や映画館の整備など、楽しみやすい環境もますます整いつつある。
若い男性カップルの愛と家族の姿
ベトナムの新作映画「Thua me con di」(英題:Goodbye Mother)が8月中旬に公開され、先日、映画館に観に行った。主人公は、アメリカに移住した若いベトナム人男性で、アメリカで知り合ったパートナーのベトナム人男性とともに久々にふるさとを訪ねるという筋立て。
切り口や楽しみ方は受け手によって異なると思う。本作品の予告編がyoutubeで見られるので末尾に記しておく。ご覧になると分かるように、男性カップルに焦点を当てた作りになっている(予告編には他にもいくつかのバージョンがある)。性的マイノリティーに向き合った作品として注目されているが、それ以外に経済発展のさなかにあっても家長制度というのはずっしりと根を下ろし、古くからの倫理観や家族観を見て取れる作品としても興味深い。さらに、ベトナムを語る上で不可欠な”越僑”という存在。実に見応えがあった。
20年ほど前からベトナム映画や映画を取り巻く環境を見てきた端くれとしては、感無量というか、時の流れにおののくというか、あれやこれやと気持ちの整理がつかず、ストーリーの流れに身を任せるのにしばし時間が必要だった。
というのも、1990年代後半はベトナム映画を取り巻く環境は全く異なっていたからだ。