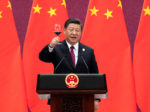世界遺産の街が直面する現実
ラオスに見るオーバーツーリズムのジレンマ
- 2020/2/26
「ラオスにいったい何があるんですか?」という異色のタイトルが話題を呼んだ村上春樹の人気紀行文集。その中に収録されている「大いなるメコンの畔で」を読んだ人も多いだろう。街全体が世界遺産に登録されているルアンプラバンが舞台のエッセイだ。ラオスについては、このほかにも、中国が支援する鉄道建設が2021年の建国記念日にあたる12月2日の開通を目指して進められていたり、韓国のソウルとビエンチャンの間に格安航空会社(LCC)が相次いで就航したりと、近年、急速に関心が高まっている。そんな同国経済のけん引役として、特に期待が寄せられる古都ルアンプラバンの今をお伝えする。
僧侶の托鉢で始まる古都の一日
隣国タイと同様、ラオスは上座部仏教の国で、僧侶たちは妻帯や飲酒を禁じる227の厳しい戒律を守っている。特に、同国で最も信仰心が篤いと言われるルアンプラバンの朝は早い。
街の中心部、サッカリン通りにある古刹ワット・セーンスッカラム。3時45分、暗闇と静寂を打ち破るように寺院の鐘が「カーンカーン」と鳴るのに続き、「ドーンドーン」と太鼓が響く。星が満天に輝く中、僧侶たちの1日が始まる。
水浴びをし、朝の読経を終えると、空が白み始めるのに合わせ、太鼓の合図で寺院ごとに托鉢に出かける。季節にもよるが、だいたい5時半から6時の間に行われることが多い。
この托鉢で人々から寄進されたものが、一日2回の彼らの食事となる。裸足に黄衣をまとった僧侶たちは、おのおの鉢を抱え、高僧を先頭に10人、20人が一列に並び、表情を変えることなく無言で歩く。まだ幼い顔の少年僧もいる。
托鉢が始まると、道路は封鎖される。サッカリン通りは、托鉢体験ができるエリアとして観光客に人気だ。この光景を一目見ようと集まってくる人々のために、沿道には夜明け前からゴザが敷かれ、椅子が並べられる。モチ米、ゴザ、椅子、衣装などの「托鉢セット」を貸し出してくれる旅行会社もあれば、喜捨用に主食のモチ米とお菓子をセットで売る出店まで出現する。
その一方で、「露出の多い服装を控える」「帽子や靴を脱ぐ」「僧侶には触れない」「近距離から撮影しない」「フラッシュを使用しない」といった注意事項がイラストや写真とともにラオス語や英語、中国語で描かれた看板が設置されているのを見ると、ラオスの伝統や文化を知らずに訪れる外国人のトラブルが多いことも伺える。
ルアンプラバンの托鉢は、国内で最も荘厳だと言われている。中でも、10の寺院から約200人の僧侶が托鉢に歩くこの通りの托鉢は、壮観だ。沿道には、托鉢を体験したい観光客や、写真撮影が目当ての人々が集まり、スマホ片手に「インスタ映え」を狙う。いざ僧侶が鉄鉢を手に近づいてくると、辺りは「托鉢撮影の現場」と化して騒然とする。
肝心の托鉢の風景も、昔とは少し変わってきた。観光客が特に多い中心部では、次々と喜捨されるモチ米で鉢がすぐに一杯になるため、僧侶たちはその都度、沿道に数メートルおきに置かれているプラスチック製の籠に中身を空け、鉢を空にするようになったのだ。一見すると、モチ米を捨てているように見えなくもない。実際、その籠をゴミ箱と勘違いし、ゴミを捨てる観光客もいるほどだ。
もちろん、この籠の中のモチ米は捨てられているわけではなく、托鉢が終わった後に一カ所に集められ、地域の住民、特に貧困層に分配されているという。実際、スッカリン通りの端で10人ほどの子どもたちがナイロン袋を広げて座り、僧侶たちがその中にモチ米を入れているのを見かけた。