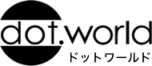世界遺産の街が直面する現実
ラオスに見るオーバーツーリズムのジレンマ
- 2020/2/26
飛騨高山と経験を共有
内陸国のラオスは産業に乏しく、政府は後発開発途上国からの脱出に躍起だ。冒頭で触れた中国が支援する鉄道建設は、中国国境のボーテンとラオスの首都ビエンチャンを結ぶ構想で、ルアンプラバンにも新駅が完成する予定であるため、観光客のさらなる増加が期待されている。
しかし、本来の意味での信仰心や喜捨の精神はともかく、いまやルアンプラバンの托鉢は、世界遺産のブランドに引き寄せられる外国人観光客によって支えられているのが実態だ。観光客の増加が歴史的な景観や文化的な魅力を招いているにも関わらず、住民の姿が消えて空洞化が進む中心部で伝統的な托鉢を支えるのは観光客しかいない現状は、皮肉としか言いようがない。オーバーツーリズムは、世界遺産の観光地ならではのジレンマだと言えよう。
こうした問題は、ルアンプラバンに限らない。例えば、日本の飛騨高山も同じ問題に直面している。この両都市をつなぎ、持続的な観光開発につなげようとする取り組みが始まっている。
2019年12月末、ルアンプラバンの郊外で伝統的な地酒のラオラオをベースに新たな酒造りに挑戦しようとしているソンポンさん(50)を訪ねた。沖縄の泡盛のルーツになったとも言われるラオラオだが、アルコール度数が高く、観光客の人気が今一つで売り上げが伸び悩んでいるという。国際協力機構(JICA)の招きで昨年10月に飛騨高山を訪れ、酒の醸造方法から販売まで学んだソンポンさんは、その知見を新しい酒造りに生かそうと意欲を燃やす。「飛騨高山の取り組みは、非常に新鮮だった。これからは、ラオスの伝統の上に飲みやすい酒を造り、収入向上につなげたい」。
中国頼みの経済の行方は
ルアンプラバンの中心部で出会った僧籍40年の老僧は、喜捨されたモチ米をプラスチック籠に入れることについて、「地元の困窮者に配っており、慈悲喜捨の仏教の精神に反しない」と語った。フランス植民地下で起きた内戦と社会主義革命を経験し、仏教の弾圧も生き延びた老僧は、「すべては諸行無常で時代と共に変わる」と言いたかったのだろうか。
ルアンプラバンの街を一望するプーシーの丘に登ると、鉄道のトンネル工事のために緑の山が切り崩されているのが見えた。現場に行く途中に通った中国国境ボーテンに至る道路沿い並ぶレストランやホテルの看板も中国語ばかりで、この国の中国経済への依存度の高さを再確認する訪問となったが、その後、春節で中国に帰国した鉄道の建設作業員たちがコロナウィルス騒ぎでラオスに戻れず、工事が中断していると聞いた。ルアンプラバンでも、中国人観光客の姿が消えたという。一国に依存し過ぎる経済発展のリスクの大きさが示された形だ。
経済的貧困と隣合わせの世界遺産の街は今後、どのように変わっていくのだろう。ふと、心配になった。