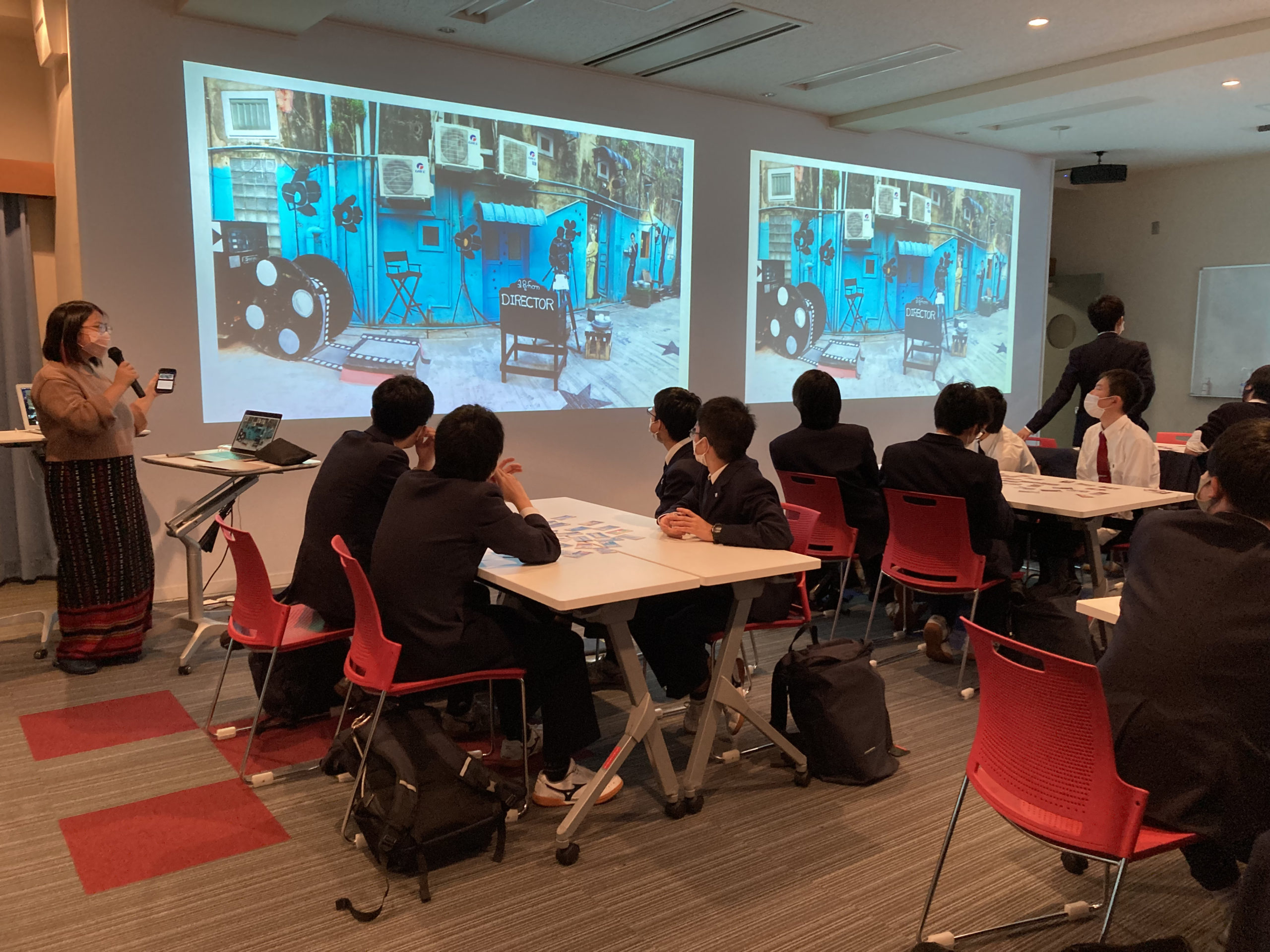かるたで広がれ、ミャンマーへの共感
未来を諦めない若者たちが開く世界
- 2022/1/16
2021年2月1日のクーデターから間もなく1年が経とうとしているミャンマー。デモ隊の背後から突っ込む警察車両や、生きたまま焼かれる人々、空爆を受け炎を上げる村など、現地からは今も連日のように悲惨なニュースが伝えられ、拘束者や犠牲者は増え続けている。そんな中、平和で穏やかだった頃の生活や文化をかるたで伝え、日本の学びを変えようという挑戦が注目を集めている。製作費など150万円の寄付を呼び掛けるクラウドファンディングは1週間で目標額を達成した。「あの日」を現地で経験した日本人の若者が見たミャンマーの姿と、賛同者の思いを追った。
一夜にして変わった街
「黄色いパダウが告げる新年」、「朝の托鉢から1日が始まる」、「レーダンマーケットは庶民の台所」―。色鮮やかな写真が印刷された「あ」から「わ」まで44枚の絵札と、平易な言葉で綴られた読み札から、生き生きとしたミャンマーの情景が目の前に広がる。この日、印刷所から受け取ってきたばかりの「Yangonかるた」を手に、野中優那さんは嬉しそうだった。現在、高校1年生。はにかんだ笑顔はティーンエイジャーらしく初々しいが、ひとたび口を開けば理路整然とよどみなく思いを語り、大人顔負けの冷静さと思慮深さを見せる。
中学2年生に進級した2019年4月から卒業までの2年間、父親の仕事で家族とヤンゴンに住み、現地の日本人学校に通っていた野中さん。コロナ禍の広がりでオンライン授業が多かったが、ミャンマーの若者向けに職業紹介ビデオを制作する会社でインターンを経験したり、家族で街を散歩したり、夕陽を見に行ったりする機会もあった。市内の環状鉄道を走る日本の中古車両や、日常的に民族衣装を着る人々に驚いたし、ミャンマー語を教えてくれる先生や、現地で出会った人々が話すきれいな日本語も印象的だった。
2021年1月に入ると感染が収束し始め、「卒業式は対面で集まれるかも」と期待を膨らませていたが、2月1日にクーデターが発生して、景色は一変。道路という道路は軍に反対する人々で埋め尽くされ、街は抗議の声であふれた。
そんな中で野中さんの心をとらえたのは、ミャンマー語の先生をはじめ、この前までごく普通に暮らしていた若者たちが、音楽を奏で、警察官に花や水を手渡しながら、平和的かつユニークな方法で抗議の意志を示す姿だった。顔を覚えられないようにデモ隊の最前列を定期的に入れ替え、SNSでは特定の投稿を拡散する代わりに皆が同じ内容を一斉にアップし、情報源を伏せるなど、見事に統率が取れていることにも驚いた。彼らの姿に、むしろ国の未来とエネルギーを感じながら、野中さんは高校進学のため3月に帰国した。
帰国後に襲われた違和感
しかし、情勢はみるみる悪化する。軍が人々に銃口を向けるようになり、犠牲者や拘束者が日に日に増える中、日本で新生活を開始した野中さんは、怒りにも似た強い違和感に立て続けに襲われる。
最初は、現地の若者たちの姿を伝えようと帰国早々にアップしたYouTube動画に「そもそも軍に武力を持たせたのが間違い」「民衆が早く追い出していれば良かったのに」という書き込みがあった時だ。長年にわたり軍が社会の実権を握っていたミャンマーでは、2011年から10年かけて徐々に民主化が進み、ようやくこれから実質的に軍の支配から離れようとしていたのに、あまりにも事実を知らないコメントで、「ズレている」と感じた。
入学した高校で自己紹介し、「危ない国から帰って来られて良かったね」と周りから声をかけられた時も、他人事だと感じ、素直にうなずけなかった。「穏やかで優しい人々が暮らす国だと知っている自分が何かしなければ」との思いがこみ上げた。
とはいえ、お金も知名度もない若者に何ができるのか。いや、現地を知っているからこそできることがあるはずだ。兄や弟と一緒にヤンゴンで撮った写真を見返しながら話し合う中、違和感を抱いた書き込みも発言もミャンマーが知られていないためだと気づき、まずは自分たちが見ていた平和で穏やかな現地の暮らしを知ってもらおうと決めた。伝える手段として「かるた」を選んだのは、「性別や年齢に関わらず、誰でも楽しめる」からだ。ミャンマーに関心を持つきっかけを提供し、現状を知ってもらうことで、共に日本とミャンマーの未来をつなげることができるのではないか―。若者ならではの支援の形が徐々に見え始め、ミャンマー語を学ぶ大学生らも仲間に加わると、プロジェクトが本格的に動き出した。
特に力を入れたのが、ブックレットだ。かるたの絵札に使われている写真の解説や、人々の人柄が伝わるエピソードを紹介したコラムなども入れ、現地の様子が臨場感とともに伝わるように工夫し、現地に詳しい通訳や識者らの協力も得て校正も入念に行った。
選べない運命を嘆かない姿
野中さんがミャンマーの若者たちのことを他人事に思えないのには、理由がある。1つは、3歳上の兄の存在だ。文字を手で書くことが難しい「書字障害」がある兄は、日本では高校からことごとく受け入れを拒否され、学びの道を閉ざされた。しかし、父親のベトナム赴任を機に現地のインターナショナルスクールに入学し、パソコンでノートを取ることが認められると、「書けない」ことは兄にとって障害ではなくなった。「今は英語を話せないことの方が大変だ」と笑う兄を見て、障害は技術でカバーできることと、何が障害になるかは環境で変わることを知った。その後も自分の書字障害を嘆くことなく学び続け、昨春、国際バカロレアでオランダにある大学に進学を果たした兄の姿と、クーデターという、自分で選べない運命に巻き込まれながらも未来を諦めないミャンマーの若者たちの姿が重なった。
また、人権侵害が続いているにも関わらず国際社会が動かないのを見て、「日本に暮らす自分たちもいつ同じ状況になってもおかしくない」と強い危機感も感じた。
しかし、熱い思いの一方で、野中さん自身の行動は冷静で慎重だ。「家族とご飯を食べ、学校に通い、夢を抱き、恋をしていた日々が突然、壊されれば怒って当然」「来るはずだった明日が奪われた理不尽さを世界に訴える彼らと、日本にいる自分たちは同じ時代を生きている」と共感するものの、「日本人の自分が抗議デモに行くと国際問題になる」ため、参加しないと決めている。「日本人が彼らを邪魔することがあってはいけない」と繰り返す言葉は、自らに言い聞かせているようでもある。
ミャンマー語の先生やインターン先の人々を気に懸けながら連絡を控えているのも、「“元気ですか”と聞くのは、返事をもらって安心したいという自己満足に過ぎない」との思いからだ。「今日を生きのびるための生活費や食料、医薬品を必要としている人や、軍を今すぐなんとかしてほしいと願う人の力にはなれないため、当事者には“何をのんきなことを”と思われるかもしれない」「中途半端な気持ちで連絡したくない」という言葉に、複雑な思いがにじむ。