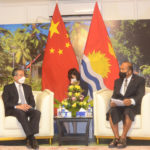太平洋島嶼国で深刻化するプラごみ問題
海をめぐって顕在化する先進国と途上国の3つの対立点
- 2023/8/22
埋まらない意識の差と日本の取るべき道
このように、太平洋島嶼国の国々には「他国とも海でつながっている」「先進国や新興国で生産・消費されるプラスチック量を減らせば、島国の環境が改善される」という認識が共有されている。既存のプラスチック廃棄物の管理にとどまらず、そのライフサイクルにもアプローチすべきだという立場である。
では、肝心のライフサイクル上流に位置する先進国や新興国の意識はどうかと言えば、都市部に住む多くの住民の目には、残念ながらいまだにひっ迫した事態とは映っておらず、生活上の利便性を犠牲にしたくない気持ちの方が強いように思われる。
また、プラスチック製品削減の動きが、いわゆる意識の高いエリート階層のアジェンダとして受け取られ、労働者層や中間層には響いていないように見える。実際、安価で大量に生産できるプラスチック製の袋や容器が規制されれば、暮らしに余裕のない層の家計はさらに苦しくなるだろう。
さらに、一見、環境に優しい取り組みのように見えるポリ袋の禁止についても、「レジ袋より紙袋やエコバックの方が水路に入り込まないという点で優れているが、嵩も重さもある分、製造と輸送により多くのエネルギーを消費し、炭素排出量が増える」という指摘もある。
加えて、米中西部のイリノイ州シカゴ市では、「再利用できる」という触れ込みで導入された厚手のレジ袋をほとんどの客がすぐに捨ててしまったため、かえってプラごみが増えてしまったという。
このように、太平洋島嶼国が現状の打破に向けて希望を託す「国際プラスチック条約」は、必ずしも所期の結果をもたらすとは限らない。多くの島嶼国住民が「先進国の失敗のツケを一方的に支払わされている」と感じている処理水問題や海水面上昇の問題と異なり、プラごみは、島嶼国の人々自身も輸入や消費を通じて問題に加担しているため、事態はより複雑だ。

太平洋島嶼国のプラごみ削減に日本が協力できる分野は多い © Pexels
プラスチックに関する国際条約は、2024年には締結に向けさらなる進展が見込まれるが、そうこうしている間にも埋め立て地はいっぱいになり、人々の食べる魚は汚染され、環境は悪化する。
そうした中、日本が取るべき道は明確だ。まず、島嶼国と共に「国際プラスチック条約」の推進に加わり、日本国内のプラスチック生産や消費を積極的に削減する。無償資金協力や技術供与を通じて、島嶼国のごみ処理施設の建設にも積極的に参画すべきだろう。そうすることで、日本人や島嶼国の人々をマイクロプラスチック汚染から守れるだけでなく、他国から日本に漂着するプラごみ問題についても、発言力が増す。
そのうえで、福島原発の処理水問題により悪化した島嶼国の対日感情を改善する。この地域で覇権を唱える中国が、日本の処理水放出を問題化することによって島嶼国と日本の切り離しを図ろうとする中、島嶼国に対して日本の友情をはっきり示すことは、わが国の安全保障の面で大きな意味を持つと言えよう。