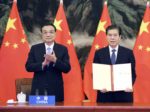ミャンマーで国軍が与党・国民民主同盟(NLD)を率いるアウンサンスーチー氏らを拘束し、「軍が国家の全権を掌握した」と宣言してから3年以上が経過しました。この間、クーデターの動きを予測できなかった反省から、30年にわたり撮りためてきた約17万枚の写真と向き合い、「見えていなかったもの」や外国人取材者としての役割を自問し続けたフォトジャーナリストの宇田有三さんが、記録された人々の営みや街の姿からミャンマーの社会を思考する新たな挑戦を始めました。時空間を超えて歴史をひも解く連載の第21話です。
㉑<大工さん>
ビルマ(ミャンマー)で1年間、暮らしていたある日、ふと違和感を覚えた。うまく言えないのだが、「何かがいつもと違う」と感じたのだ。もちろん、異国に暮らしているのだから、言語や衣食住など、生活するうえで明らかな違いがあるのは当然なのだが、そうしたことのほかにも、何か理由があるようだった。
よくよく観察すると、ミャンマーに暮らしながらも、身の回りにはいくつもの「外国」が溶け込んでいた。また、今と昔が混じり合っていることにも気が付いた。思えば、1990年代から2020年代にかけて、こうした時空が混然一体となった事象をミャンマーのいたるところで見かけたようだ。たとえば、テーブルや椅子などの家具を作ったり、家を建てたりする大工さんの道具にも、それはよく表れていた。ほんの一例を可視化してみたい。

朝からバイクを走らせ、昼食にしようと食堂に入った時のこと。注文を終え、さあ食べようと座り直し、テーブスに椅子 を寄せた瞬間、膝が当たった。「あれ、どうした?」と疑問がわいたのもつかの間、身長177cmの私にこのテーブルは低過ぎるのだと気が付いた。そこで、次の疑問がわいた。家具屋さんは、どんな基準でこのテーブルの高さを決めたのか、と。(ザガイン地域・モンユワ、2018年)(c) 筆者撮影

ビルマ(ミャンマー)では、どんな基準にのっとってテーブルやイスの高さを決めているのだろう…。そんな疑問を頭の隅に置きながら、取材を続けていたある日、ザガイン地域の中で特に大きなシュエボーの町で家具を作っている工房におじゃますることにした。訪ねてまず驚いたのは、大工さんが女性だったことだ。大工は男だと勝手に決めつけていたことに、その時、初めて気がついた。許可をもらい、自由に撮影することができた。(ザガイン地域・シュエボー、2018年)(c) 筆者撮影

ビルマ(ミャンマー)の大工さんは一般的にどんな工具を使っているのか興味があり、見せてもらうと、のこぎりは押して切るタイプだった。また、テーブルに膝を当てて以来、高さの基準が特に気になっていたため、メジャーにどんな目盛りが刻まれているのかも知りたかった。この工房では、アラビア数字で記されたメートル・メジャーと、アラビア数字が刻まれた
インチとセンチが両方、アラビア数字で記された直角定規を使っていた。(c) 筆者撮影

町中で見られる、ごく一般的な喫茶店の朝食風景。ビニール製の椅子やテーブルは、これがミャンマー(ビルマ)で最も一般的な高さだと思われる。(ザガイン地域・モンユワ、2018年)(c) 筆者撮影

農村部で見られる典型的な喫茶店の様子。テーブルや椅子の高さも、よくあるタイプで、地面に近い。奥には仏壇や家族写真があり、テーブルには共用のお茶碗が置かれている。最新の広告・宣伝のポスターも飾られ、LED照明が天井から吊るされている。(ザガイン地域・モンユワ郊外、2018年)(c) 筆者撮影

家屋の建設風景。水準器を使用して水平を測っている。(マグウェ地域・ガンゴー~ザガイン地域・カレーミョ間、2018年)(c) 筆者撮影

シンピュー式(得度式)で使われる伝統的な飾り牛車を制作する工房におじゃまして、写真を撮らせてもらうことにした。(ザガイン地域・シュエボー郊外、2018年)(c) 筆者撮影

伝統的な飾り牛車を制作する工房の大工さんが使う鑿(のみ)。(ザガイン地域・シュエボー郊外、2018年)(c) 筆者撮影

伝統的な飾り牛車を制作する工房の大工さんが使うハンマー・鑿(のみ)・定規・のこぎり。定規はインチとセンチの目盛りが両方、アラビア数字で刻まれている。(c) 筆者撮影

ビルマ(ミャンマー)の南部をバイクで走り抜けた際、町中でよく見かける喫茶店を観察してみた。ちょうど身長177cmの私とほぼ同じぐらいの背格好の男性が腰かけていたが、椅子が低いため、膝から太股までテーブルの下に入っていた。(タニンダイー地域・ベイッ〈英語ではMyeikと表記〉、2019年)(c) 筆者撮影

現在も町中でよく見られる喫茶店兼軽食屋。プラスチック製のテーブルも椅子も、この高さが一般的だ。現在でも新聞を読んでいる姿が印象に残った。(ヤンゴン市内、2019年)(c) 筆者撮影

今から22年前のヤンゴンで見られた路上喫茶店。当時は、この高さのテーブルや椅子を町中でよく見かけた。(ヤンゴン市内、2002年)(c) 筆者撮影

ヤンゴンの中華街(チャイナタウン)にある工房で働く大工さん。(ヤンゴン、2008年)(c) 筆者撮影

ヤンゴンの中華街(チャイナタウン)にある工房で働く大工さんが折尺を使っていた。刻まれている目盛りの単位はインチで、アラビア数字で表記されている。(ヤンゴン、2008年)(c) 筆者撮影

ヤンゴンの中華街(チャイナタウン)にある工房で働く大工さんが使っていた中国製の折尺。刻まれている目盛りの単位はインチで、アラビア数字で表記されている。(ヤンゴン、2008年)(c) 筆者撮影

日本で木造家屋を作っている40代の棟梁が使っている鑿(のみ)と直角定規の一部を見せてもらった。刻まれている目盛りの単位はセンチで、アラビア数字で表記されている。(日本、2024年)(c) 筆者撮影

日本で木造家屋を作っている40代の棟梁に、作業中の柱の一部を見せてもらった。目印に記しているのは、ひらがなとローマ字、漢数字だ。(日本、2024年)(c) 筆者撮影
-

-
過去31年間で訪れた場所 / Google Mapより筆者作成
-

-
時にはバイクにまたがり各地を走り回った(c) 筆者提供