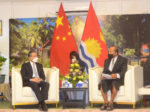タイ国境の「忘れられた」ミャンマー難民の今
流入から35年経っても祖国への帰還進まず
- 2019/12/30
難民の帰還の行方は
タイ国境に近いミャンマー・カレン州の街、レケイコー村を訪ねた。高原の山麓に広がるこの村は、2015年に建設されて以来、帰還難民の受け入れを積極的に進めてきただけあって、現在は799世帯、3,199人が暮らす。人口の1割強が難民キャンプからの帰還難民に相当する計算だ。将来的には受け入れをさらに進め、1,500世帯、6,000人規模の村に拡大することが構想されている。
住民委員会が実施した最新の調査では、住民の6割が日々、国境を超えてタイのメソトの建設現場や縫製工場などで日雇い労働に従事し、残りの人々は村の近くで日雇いで農作業に就いていることが分かった。
タイ国内には、こうしたミャンマーからの移民労働者が推定300万人暮らしていると言われる。ミャンマーの農村部にはこれといった産業もないことが原因だが、せっかく難民キャンプから祖国に帰還しても、仕事がなければ仕事を求めてタイに戻らざるを得ないという現実がある。
また、村によって温度差はあるものの、帰還難民を受け入れる村人の側も概して複雑な感情やしこりを抱くことが指摘されている。村に余裕はなく、自分たちが食べるだけで精一杯なのに、帰還難民が増えれば、農地や仕事の取り合いに発展しかねないためだ。実際、かつてSVAがカンボジア難民を支援した際も、国内に留まり苦労した人々が帰還難民を「逃げて楽をした者」と蔑視する傾向は見られた。
ミャンマーで民政移管が実現して以来、支援は国境の難民キャンプからミャンマー国内へと移っているが、住民の尊厳が守られる安全な「自主的帰還」が実現し、国境から難民キャンプがなくなる日まで、国際社会はその推移を見守り、自立を継続的に支援する必要性があるのは言うまでもない。
「難民は社会を映し出す鏡」――。難民支援の究極の目的は、難民がいなくなることなのだから。