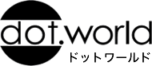タイ国境の「忘れられた」ミャンマー難民の今
流入から35年経っても祖国への帰還進まず
- 2019/12/30
帰還か第三国定住か、家族で割れる意見
祖国ミャンマーへの帰還が進まないことを受けて2005年より始まったのが、第三国定住プログラムだ。2019年11月までに11万3,113人が定住したと言われ、最も多い定住先は、米国の8万8,709人。二番目はオ―スラトリアの1万3,274人、カナダ5,226人と続く。もっとも、米国は2013年に第三国定住の募集を締め切ったため、現在は定住先になる道が閉ざされている。
日本も2010年、アジアで初めて第三国定住制度を導入し、タイの難民キャンプで暮らすミャンマー人を受け入れたのを皮切りに、2014年までの5年間で18家族86人の来日を認めた。また、2016年10月には、タイとミャンマー政府の合意の下、UNHCRや国際移住機関(IOM)など国際機関が連携して自主帰還が始まり、71人が帰還。これまで4年間で4回にわたり、7カ所のキャンプから計273家族、1,039人が帰還を果たしている。しかし、メラ難民キャンプの内務省の担当官は、「このペ―スでは、国境の難民が全員、帰還するまでに何十年、いや何百年かかるか分からない」と、厳しい見方を示す。
一方、肝心のタイ政府は、2014年に難民の流入を厳しく制限する方針を打ち出し、難民としての登録も、タイ国内への定住も認めないことを決めたたため、タイ経由で第三国定住する道も、タイ国内に定住の道も事実上、閉ざされ、現在は、祖国への帰還の道だけが残されている。
もっとも、時間の経過とともにキャンプ生まれの子どもたちが増えるにつれ、キャンプ内の家族の中では、故郷に対する意識に変化が生まれているようだ。帰還を望む祖父母世代に対し、より良い仕事と質の高い教育を求め、親世代やキャンプ生まれの子ども世代は第三国定住を望むようになり、家族の中でも意見が多様化しつつある。