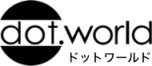内戦に揺れるミャンマーの少数民族ムロ
ラカイン州逃れ生活再建目指す
- 2020/8/7
手作りのキャンプ建設
多くの人は難民キャンプと聞くと、戦争から逃れたかわいそうな人々が気力なく援助を待っているようなイメージを思い浮かべるだろう。しかし、このキャンプはその例とは大きく異なる雰囲気がある。
キャンプにある小屋は、竹の骨組みを笹で編んだ壁で囲み、草ぶきの屋根をかけたもの。ミャンマーの農村部によく見られる高床式住居だ。キャンプにはすでに30家族がいるのもの、小屋は9軒しか建設できておらず、多くの家族は大きめの小屋にごちゃまぜで暮らしている。その必要な残りの家を建設するために、若手を中心とした避難者が竹を切ったり、資材を運んだりと、せっせと働いているのだ。
クリス・テイン牧師は、「建設費が足りないので、柱や壁などの資材は寄付してもらっている。資材がそろえば、みんなで力を合わせて組み上げて、一日あれば一軒建てることができる」と、説明する。水は井戸水を使っているが、衛生状態に配慮してトイレをいち早く設置した。ソーラー発電機を持ち込んで、電気を使う人もいる。暇があれば、竹を編んで籠を作り、生活を支える。将来的には、保育園など子どもの面倒を見る施設も作りたいという。
ここでは、避難民の多くが故郷に帰ることを望まず、ヤンゴンで新しい生活を始めようとしている。前述の48歳の男性は「もう村には帰りたくない。何でもいいからヤンゴンで仕事を探して、家族と暮らしたい」と話す。それだけ恐ろしい思いと苦労を重ねてきたということだろう。軍用機の爆撃を受けて家族で薮に隠れたという29歳男性は、村への帰還を「自分の墓を掘りに行くようなもの」と、表現した。
ここでの暮らしは、収入の確保、土地問題、子どもの教育、周辺住民の理解、法的地位など、彼らを待ち受ける課題が大きいことは想像に難くない。ただ、このキャンプが新生活を作ろうとする人たちの熱気にあふれていることも、事実なのだ。