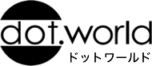米国の小中学校で対面授業の再開巡り論争
コロナ禍で浮き彫りになった職種の不公平感と人種間格差
- 2020/10/2
教職員はゼロリスクを要求
他方、教員側にも言い分はある。第一に、「契約上、医療従事者のように健康リスクが存在しても働かなければならないという義務を負わない」という主張だ。もっとも、この点については、生鮮食品店や食肉工場、警察職員、救命救急、運送業など、他の必須要員も同じだとの指摘がある。
第二に、年齢上および既往症上の理由だ。米国では幼稚園に通う園児と小中学校の児童・生徒が約5640万人おり、彼らを指導する教職員は約370万人だが、その3分の1は感染リスクが有意に上昇する50代以上であり、特にスクールバスの運転手は、4分の3が55歳以上だと言われている。アメリカ教員連盟(AFT)の発表によると、組合に加盟している教職員だけでもこれまでに210人がコロナによって死亡したという。この中にはリスクが比較的低いとされる20代や30代の者も含まれていた。
この事態を受け、ニューヨーク市の統一教員連盟(UFT)のマイケル・マルグルー会長は、「あらゆる感染予防策がとられたとしても、学校に出入りするすべての者が感染していないことが証明されない限り、教師は出勤しない」と述べ、ゼロリスクを要求した。低所得層のヒスパニック系家族が特に多いカリフォルニア州のサンディエゴをはじめ、ロサンゼルスやシカゴなどの大都市でも「安全が確保されていない」として、今なお全面的にオンライン授業が続いている。
これについて、シカゴ教職員組合のジェシー・シャーキー委員長は、「組合のストライキによって完全なオンライン授業が実現したことは、教員、生徒、保護者すべてにとって勝利だ」と宣言した。また、サウスカロライナ州教育協会のシェリー・イースト会長も、「教職員は確かに必須要員だが、だからと言って自分の身を危険にさらしていいということではない。われわれは医療従事者ではなく、子どもを指導するために存在している」との声明を発表した。
「子どもの安全を第一に考えて」というのは、こうした議論の際に必ず持ち出される決まり文句だ。しかし、広く知られている通り、子どもが感染したり重症化したりする確率は極めて低く、バーやレストランでクラスター感染が相次いでも、学校がクラスター化する事例はほとんどない。さらに、仕事を持っている保護者の多くが対面授業を望み、教職員側がオンライン授業を主張しているという構図から見ても、この問題の根が子どもより大人の安全面にあるのは明らかだ。
高い組織力と政治力を持ち、オンライン授業を要求して通すことができる教職員と、そうした「ぜいたく」がかなわない必須要員の職に就いている保護者の間に溝が生まれ、社会が分断されて教育に不可欠な学校への信頼が揺らぎつつあるのは、ゆゆしき事態と言うほかない。
米国経済のカギを握る世論の行方
とはいえ、教職員にも同情すべき点はある。米国社会において、多くの教職員は薄給である上、共通テストで教え子の成績が悪ければ免職で切り捨てられかねない。精神面の成長を促す献身的な指導もほぼ評価されないという、実に損な役回りの職業である上、さらに命まで捧げろというのは確かに酷な面もある。
しかし、米国社会がコロナ禍から回復できるか否かは、学校での対面授業がいつ再開できるか次第であると言っても過言ではない。今後、子どもが登校しないために親が家を空けられず、失業や収入減、住居の強制立ち退きにつながったり、ビジネスの再開が遅れ景気の後退が深刻化したりすることがあれば、教職員への風当たりは一層強まるだろう。
この問題の背景に、大統領選の主要争点の1つともなっているコロナ対応を巡るリベラル派と保守派の対立があることは否定できない。しかし、現状は「リスクの高い対面授業再開を求めるトランプ」と「リスクが高まれば再び学校のロックダウンを求めるバイデン」という単純な二元論では捉えられないほど複雑であり、この議論も、党派による対立から、徐々に「教職員」「親」「企業」など、それぞれの立場の違いによる対立へと形を変えつつあるように思われる。
米国の将来を担う子どもたちが対面授業に戻り、親たちが職場に完全復帰することで米経済が持ち直すか否かは、授業の形式をめぐる世論の行方に大きく左右されそうだ。